Twitter(X)で成功した採用事例5選!SNSを活用した求人戦略とは?
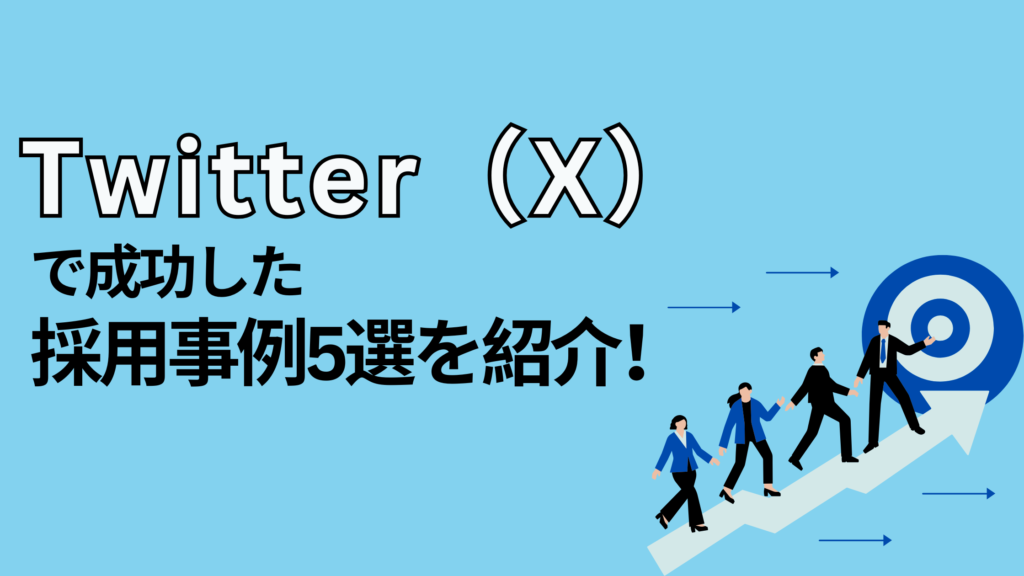
X(旧Twitter)を活用した採用活動が、静かに勢いを増しています。企業アカウントによる情報発信や、求職者とのスムーズなやり取りを通じて、自社にマッチする人材と出会う手段として注目されているからです。しかし、「どのように使えば効果が出るのか」「本当に成果につながるのか」といった疑問を持つ方も少なくありません。本記事では、実際に成果を上げた国内の成功事例をもとに、SNSを活用した採用戦略のヒントを明らかにしていきます。具体的な施策と運用の工夫を通じて、採用手法のアップデートを検討されている方にとって実践的な内容をお届けします。
目次
なぜ今、Twitter(X)採用が注目されているのか
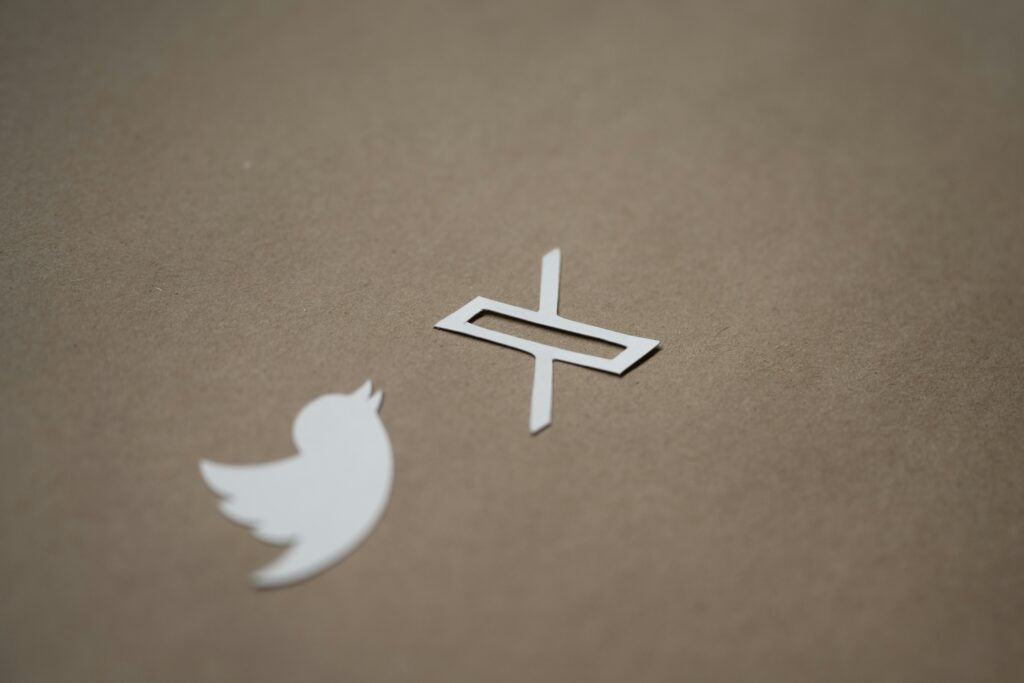
従来型採用の限界とSNSの台頭
近年、多くの企業が採用活動に課題を抱えています。求人媒体に掲載しても応募が集まらない、採用できても定着しないといった悩みが頻出しています。その背景には、従来の採用手法が候補者との接点づくりにおいて限界を迎えていることが挙げられます。とくに若年層や変化に敏感な層に対しては、旧来のメディアだけではリーチしきれない状況が生まれています。
こうしたなかで、SNSを活用した採用活動が新たな選択肢として注目されています。企業が積極的に発信し、求職者との接点を自らつくり出すアプローチが求められるようになってきたのです。特にX(旧Twitter)は、テキスト主体でスピーディに情報を届けられる特性があり、双方向のやりとりも自然に行えるため、採用活動の起点として有効です。
リアルタイム性と拡散力という特性
Xの大きな特徴の一つが、リアルタイム性の高さです。企業の日常や雰囲気、業務の一部をその場で発信することができ、タイムリーな情報提供が可能になります。求人情報を出すだけでなく、その背景や意図、現場の声といった温度感を伝えることで、単なる募集以上の意味を持たせることができます。
さらに、ユーザーによるリポストや引用といった行動によって、情報が自動的に広がる構造も魅力です。自社のフォロワー以外にも届く可能性があり、偶然の発見や興味喚起を誘発する力があります。これにより、意図していなかった層との接点が生まれ、従来とは異なる人材にアプローチすることも可能です。
採用コストやスピード面での優位性
Xを使った採用は、費用面でもメリットがあるといわれています。多くの機能が無料で利用できるため、初期コストやランニングコストを抑えた運用が可能です。投稿にかかる時間や工数を最小限にしながらも、情報を多くの人に届けることができる点で、他の採用チャネルとは一線を画します。
また、反応が得られた際にはすぐにダイレクトメッセージなどを活用して接触できるため、採用までのスピード感にも期待が持てます。エントリーから面談への移行がスムーズであるほど、候補者のモチベーションを保ったまま次のフェーズへ進めることができ、採用の質と量の両立にもつながります。
こうした背景から、特にスピードとコストの両面を意識する企業にとって、Xを使った採用は戦略的に非常に魅力的な選択肢になっています。
Twitter(X)採用の基本的な仕組みと運用方法
公式アカウントによる情報発信のポイント
Twitterでの採用活動は、まず企業アカウントの運用から始まります。ここでは、求人情報をただ発信するのではなく、日常的な投稿を通じて、企業の雰囲気や働く人の姿を可視化することが重要です。日々の投稿が企業の印象を形づくり、興味を持ったユーザーが自然とプロフィールや過去の投稿を確認する流れが生まれます。そのため、投稿内容は求人情報に限らず、日常の出来事や働き方に関する発信など、多様な切り口を取り入れることが効果的です。
加えて、プロフィール欄の整備や固定ツイートの活用も欠かせません。ユーザーがアカウントを訪れたときに、採用に関する情報がすぐに視認できる構成になっていれば、興味を持った人材との接点を逃しにくくなります。採用専用アカウントを用意する場合には、投稿内容や文体に一貫性を持たせることが、信頼感を高める要素となります。
投稿の頻度と内容のバランス
アカウントの運用においては、投稿の頻度と内容のバランスが非常に重要です。過剰に投稿しすぎると情報過多となり、フォロワーの関心を失う可能性があります。一方で、間隔が空きすぎてしまうと、アカウントの存在感が薄れ、採用活動の鮮度が伝わらなくなります。理想的なのは、情報提供と共感の発信をバランスよく織り交ぜることです。
たとえば、募集職種の紹介や選考スケジュールの案内などの情報性の高い投稿と、現場の様子や働く社員の声など、共感を呼びやすい内容の投稿を組み合わせることで、読者にとって価値のある情報源としての役割を果たします。このような投稿を継続して行うことで、アカウントの認知と信頼が積み重なり、応募者数の増加につながる可能性があります。
ハッシュタグと検索導線の活用
Twitter採用の成果を左右する要素の一つが、ハッシュタグの活用です。求人に関連したキーワードをハッシュタグ化することで、検索からの流入や関連性のある情報との接続がしやすくなります。求職者が興味を持つキーワードやトレンドを適切に取り入れることが、効果的な発信につながります。
また、ハッシュタグは単に付けるだけでなく、投稿内容と意味が連動しているかどうかが問われます。情報の整理と発信の設計が伴ってこそ、検索された際に適切に文脈が伝わり、アカウントへの信頼感も高まります。日本国内で定着しているハッシュタグの例を活用することで、より広い層へのリーチが可能となります。
ハッシュタグに加えて、画像や動画といった視覚情報を投稿に添えることで、印象に残りやすい情報発信が実現します。採用ページへのリンクを投稿内に添える工夫も、有効な導線設計の一部です。
他SNSとの違いはどこにあるのか

InstagramやTikTokとの採用目的の差異
SNSを採用活動に活用する際、どのプラットフォームを選ぶかは目的によって変わります。InstagramやTikTokは、視覚的な魅力を伝えるのに優れた媒体です。写真や動画を中心とした投稿により、職場の雰囲気やスタッフの人柄、店舗の内装などを直感的に訴求できます。その一方で、即時性のある情報発信や、双方向のやりとりにおいては制限があるため、採用に直接結びつけるまでの導線設計には工夫が求められます。
一方、X(旧Twitter)はテキストを主とするため、ビジュアル重視ではなく言葉での説明に適しています。募集の背景や求める人物像、仕事のやりがいなどを言語化し、詳細かつ継続的に伝えることで、応募前から価値観の共有を促進できます。また、タイムライン上で複数の投稿が一貫したトーンで流れることにより、企業のスタンスや採用姿勢を伝えやすい点も特徴です。
X特有のユーザー層と拡散構造
Xには独自のユーザー文化とコミュニケーション様式があります。匿名性が高く、ユーザー同士のつながりも比較的緩やかなため、情報の受け手が自発的に興味を持ち、行動につなげやすい傾向があります。さらに、リポスト機能を通じて他者の投稿が第三者のタイムラインに現れる仕組みは、自社アカウントのフォロワー以外にも情報を届ける機会を生み出します。
このような拡散構造は、広告的な要素を排し、自然発生的な共感を通じた拡がりを実現するうえで非常に有効です。情報が届く範囲に偶発性があるからこそ、これまで接点のなかった人材層にアプローチできる可能性も高まります。関心を持ったユーザーがその場で反応しやすい点も、採用活動との相性の良さを示しています。
向いている採用シーン・向かない場面
Xでの採用が特に向いているのは、企業の考え方やチームの雰囲気を重視した採用を行いたいケースです。たとえば、価値観の合致や柔軟な働き方、チームワークを大切にしている職場では、日々の投稿を通じた文化の発信が効果を発揮します。また、スピード感のある採用や短期的な募集にも対応しやすい点が評価されています。
一方で、業務の内容が視覚的に伝えづらい場合や、求人情報を詳細に掲載する必要がある場面では、別のチャネルと併用するほうが効果的です。また、SNS上での発信に時間やリソースを割く余裕がない場合も、成果を上げるまでの継続性が確保しづらくなるため注意が必要です。
Twitter(X)で採用に成功した5つの国内事例
1. テレビ東京:舞台裏の発信で「共感」と「楽しさ」を演出
日常投稿で“テレビ局らしさ”を表現
テレビ東京は、新卒採用アカウントで社員の日常業務や番組制作の裏側を発信しています。
ユーモアを交えた投稿を通じて「テレビ局で働く楽しさ」を自然に伝え、特にクリエイティブ職志望者の応募増加に貢献しています。
成果のポイント
-
トレンドを意識した投稿(ライブ配信・動画の活用)
-
インターン生による若者目線の投稿で共感と親近感を醸成
2. 株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA):YouTube連携で技術職にアプローチ
社員の起業家マインドをリレー形式で発信
DeNAでは、新卒向けアカウントを通じて、社員のキャリア観や起業家マインドをリレー形式で発信。
柔軟な働き方やエンジニア向けコンペ情報など、多角的なアプローチで技術職人材の採用に成功しています。
成果のポイント
-
YouTubeとの連携による動画コンテンツの拡散力
-
社員の個性を前面に出し、働くイメージの具体化
3. ナブテスコ:キャラクター×理系ターゲットで共感を獲得
ユニークなキャラで企業の“らしさ”を打ち出す
ナブテスコでは、「ナブテスコモンスターズ」というオリジナルキャラクターを活用し、
技術職あるあるや理系ネタをイラストで発信。理系層への共感と認知拡大に成功しています。
成果のポイント
-
親しみやすさを高めるキャラクター発信
-
多様な職種の魅力を社員インタビューで紹介
4. 株式会社favy:DMを活用したエンジニア採用効率化
ダイレクトメッセージで信頼を構築
favyでは、転職希望者の投稿にいち早く反応し、現場社員が直接DMを送ることで信頼関係を構築。
返信率は**77%**を誇り、ピンポイントな人材獲得につながっています。
成果のポイント
-
DM文面に企業の魅力やビジョンを明確に記載
-
部署横断で候補者情報を共有し、選定の精度を向上
5. 株式会社Kaiketsu:トレンド発信で急速なフォロワー獲得
25日間でフォロワー1,000人を突破
Kaiketsuは、採用マーケティングに特化した専用アカウントを開設し、
「#転職」などのトレンドタグやホットトピックを活用。たった25日間でフォロワー1,000人超という成果を上げています。
成果のポイント
-
1日1投稿の継続によるアカウント運用の信頼性
-
画像・動画を多用した視覚的なアプローチ
実践のために押さえておきたい準備ステップ
採用目的とターゲットの明確化
X(旧Twitter)を活用した採用活動を始めるにあたり、まず必要なのは「何を目的として採用するのか」を明確にすることです。単に人手が足りないから発信するのではなく、「どのような人材を求めているのか」「自社にどんな魅力があるのか」といった点を丁寧に洗い出すことで、発信内容の軸が定まります。
ターゲットとする層の特性を理解することも欠かせません。たとえば柔軟な働き方を求める人材に向けては、勤務体制や価値観に関する投稿が効果的です。一方で、成長環境を重視する層には、キャリアパスや教育体制に触れた投稿が響きます。誰に向けてどのような内容を届けるかを整理することが、採用活動全体の質を左右します。
投稿テーマや発信のトーンも、あらかじめ設定しておくとスムーズな運用につながります。ターゲットとする層の行動特性や価値観に合わせて情報を設計し、採用との接点を意識した発信を心がけることが、実践的な成果に結びつきやすくなります。
社内体制と役割分担の見直し
SNSの運用は、個人の裁量に任せすぎるとリスクが高まりやすいため、社内での役割分担を事前に調整しておくことが必要です。採用活動は継続性が鍵となるため、投稿の作成・承認・公開・モニタリングといった工程をチームで分担する体制づくりが求められます。
たとえば、人事担当が発信内容を企画し、広報部門が文章表現をチェックするなど、複数の視点で内容を確認できる体制はリスク軽減につながります。専任の担当者がいない場合でも、週ごとに交代するなど、継続性を維持できる工夫が重要です。
また、スケジュール管理の観点からも、投稿カレンダーの作成が効果を発揮します。事前にテーマを設定しておくことで、突発的な内容に振り回されることなく、安定した投稿頻度を保つことができます。あらかじめ準備された体制は、外部から見たときの印象にも直結します。
既存の採用チャネルとの統合視点
X単体で採用活動を完結させようとするのではなく、既存の採用チャネルとの連携も視野に入れておくことが有効です。たとえば、自社サイトの採用ページと投稿内容を連動させることで、詳細情報への導線を設計できます。また、説明会の告知や選考の進捗連絡といった情報を補完する手段としてもSNSは活用できます。
求人媒体や採用イベントといった既存の手法との役割分担を明確にすることで、SNSの情報発信が埋もれることなく、採用全体のなかで効果的に機能するようになります。単なる広報ではなく、採用活動の一部として位置づけることで、より具体的な成果につながりやすくなるのです。
さらに、Xでの発信は採用だけでなく、企業ブランディングや顧客との関係構築にも波及します。そのため、採用部門と他部署が連携し、企業として一貫した方向性でSNS運用を進めることが望まれます。情報発信を“点”で捉えるのではなく、全体のなかで“線”として活用する視点が求められます。
まとめ:Twitter(X)採用は“人柄”と“戦略”の両立が鍵
SNSでの採用活動は、企業の“人柄”を伝える手段であると同時に、明確な戦略のもとで設計しなければ効果が現れにくい取り組みです。発信する情報に一貫性と意図を持たせることで、求める人材と自然に出会える導線が育ち、結果として自社に合う採用の形が見えてきます。
